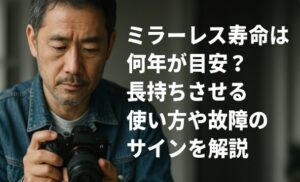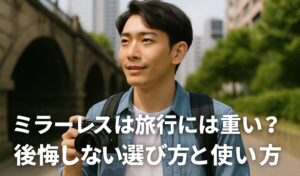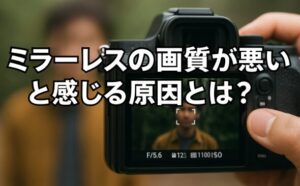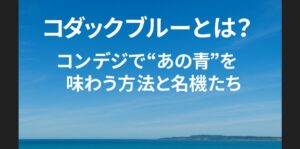「ミラーレスカメラって電池がすぐ切れるって本当?」
そんな疑問を持ってこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
確かに、ミラーレスは一眼レフと比べてバッテリーの減りが早いという特徴があります。ですが、それは“選び方”と“使い方”次第で十分カバーできるものです。
本記事では、
- なぜミラーレスは電池持ちが悪い?
- 電池が長持ちするおすすめ機種は?
- どのくらい予備バッテリーが必要?
- 節電設定やUSB給電などの運用テクニック
といった疑問に、初心者にもわかりやすくお答えしていきます。
「せっかくのシャッターチャンスをバッテリー切れで逃したくない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
ミラーレスの電池持ちって本当に悪い?購入前に知るべきこと
「ミラーレスは電池がすぐなくなる」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
この章では、なぜそのように言われるのか、そして実際にどれほどの差があるのかを解説していきます。
なぜ一眼レフよりバッテリーが減るのか?

一眼レフは、ファインダーに光を通すためのミラー機構を持ち、センサーは「シャッターを切った瞬間」にしか作動しません。つまり、カメラを構えている間はほとんど電力を使っていないのです。
一方、ミラーレスカメラはミラーを持たず、常にセンサーを動かしてライブビュー映像を映し続けています。
液晶画面や電子ビューファインダー(EVF)にも電力を常時供給しているため、シャッターを切っていなくても電池を消費するのです。
この構造の違いが、ミラーレスの「バッテリー持ちが悪い」と言われる最大の理由です。
撮影スタイルが電池持ちに与える影響

ただし、これはすべてのユーザーにとって致命的な問題というわけではありません。
実は、撮影スタイルによってバッテリーの減り方は大きく変わります。
たとえば、風景をじっくり撮る人と、スポーツや子どもの写真を連写する人では、必要な電力も消耗スピードもまるで違います。
また、「撮った後すぐに画像を何枚もチェックする」「こまめに設定変更をする」など、カメラを操作する頻度が高い人ほど電池の減りは早くなる傾向にあります。
「バッテリー不安=ミラーレスNG」ではない理由

確かに一眼レフと比較すれば、バッテリー持ちで劣るのは事実です。
しかし、近年のミラーレスはバッテリー技術や省電力設計が進化しており、運用次第で問題なく使えます。
たとえば、SonyのNP-FZ100バッテリーは、α7シリーズで最大700枚以上撮影可能とされ、旅行やイベントで1日持たせることも十分可能です。
また、USB給電対応のモデルであれば、モバイルバッテリーから補助電力を得ながら撮影することもでき、実質「無限運用」も可能です。
「ミラーレスだからやめておこう」と感じていた方も、今やそれほど神経質になる必要はありません。
このセクションでは「バッテリー=弱点」という先入観を見直していただけたかと思います。
次は、実際に「どの機種が電池持ちに優れているのか?」をランキングとともにご紹介します。
電池持ちが良いおすすめミラーレスカメラ【2025年最新版】
電池持ちが不安なら、最初から「バッテリー性能の高いカメラ」を選ぶのがもっとも確実な対策です。
このセクションでは、撮影可能枚数の指標となる「CIPA基準」に基づいて、電池が長持ちするミラーレスカメラをランキング形式で紹介します。
用途別のおすすめ機種や、USB給電やバッテリーグリップに対応したモデルも併せて解説しますので、ご自身のスタイルに合ったカメラ選びに役立ててください。
撮影枚数ランキング(CIPA基準)トップモデル

この基準での撮影可能枚数が多いほど、電池持ちの良さを客観的に比較できます。
以下は、2025年時点でCIPA基準の撮影枚数が多いミラーレス機のトップモデルです:
| 順位 | 機種名 | 撮影可能枚数(CIPA基準) |
|---|---|---|
| 1位 | Olympus OM-D E-M1X | 約870枚(EVF使用時) |
| 2位 | Sony α6600 | 約810枚 |
| 3位 | Fujifilm GFX100 | 約800枚(中判センサー) |
| 4位 | Sony α7 IV | 約580枚 |
| 5位 | Canon EOS R6 Mark II | 約580枚(液晶使用時) |
この中でもSonyのNP-FZ100バッテリーを採用しているモデルは、他と比べても圧倒的に長持ちします。カメラのサイズはやや大きくなりますが、その分バッテリー容量に余裕があり、日常撮影や旅行でも、1〜2本あれば十分に安心できるレベルです。
※注意点として、同じメーカー内でもエントリーモデルと上位機ではバッテリー規格が異なり、持ち時間が大きく変わります。
たとえばSonyのZV-E10はNP-FW50という旧型バッテリーを使っており、持続力はα6600よりもかなり劣ります。

用途別おすすめ機種(旅行/動画/静止画)

カメラ選びで大切なのは「何をどう撮りたいか」。ここではシーン別におすすめモデルを紹介します:
- 旅行や日常スナップには:Sony α7C II
→ 軽量かつコンパクトで、α7 IVと同等のバッテリー性能。街歩きや旅行中も疲れにくく、USB給電も可能でモバイルバッテリー運用もしやすい。
カバンに入れっぱなしでも邪魔にならないサイズ感も魅力です。 - 動画撮影やVlogには:Panasonic LUMIX GH6
→ 高効率のバッテリー設計に加え、動画の安定性・熱対策も優秀。USB給電で長時間録画にも対応。
特に4K60p以上での撮影が多い人には安心感があります。 - 静止画中心の撮影には:Canon EOS R8 または Fujifilm X-T5
→ 写真画質と操作性を優先したい人に。予備1本あればほぼ1日持つ安心感。
特にX-T5は手ブレ補正と省電力設計のバランスが良く、日常の持ち歩きに向いています。
「軽さ・使いやすさ」と「電池持ち」はトレードオフになりやすいため、自分の撮影スタイルに合った“バッテリー耐久バランス”を意識すると失敗が減ります。
USB給電・バッテリーグリップ対応モデルもチェック

これにより、撮影中にモバイルバッテリーから給電しつつ使用できるようになり、バッテリー切れの不安は大きく軽減されました。
たとえば以下の機種は、USB給電+撮影同時使用に対応しています:
- Sony α7シリーズ(α7 III以降)
- Canon EOS R6 / R8
- Fujifilm X-T5
- Panasonic S5 II
屋外で長時間撮影を行う人や、電源が取れない場所での撮影にはUSB給電対応モデルが強くおすすめされます。
また、バッテリーグリップに対応していれば、バッテリー2本を装着することで、稼働時間を単純に2倍に伸ばすことができます。
長時間の屋外撮影やイベントカメラマンには特に便利です。
グリップを使うことで縦構図の撮影も楽になるなど、操作性の面でもメリットがあります。
次のセクションでは、実際の撮影スタイルに応じて「どれくらいバッテリーが必要なのか?」をシミュレーションし、電池を長持ちさせる工夫についても解説していきます。
撮影スタイル別:必要な予備バッテリーの数と節電のコツ
「どれくらいバッテリーを持っていけば足りるのか?」という疑問は、ミラーレスを使う多くの人が抱える不安のひとつです。
実際には、撮影する被写体や場所、さらには気温によっても必要なバッテリー本数は変わってきます。
写真:日帰り旅行・運動会などの必要本数目安

ただし、撮影枚数が多かったり、ライブビュー表示が長時間続いたりすると、予想よりも早く電池が切れることがあります。
撮影スタイル別の目安:
- 観光・スナップ撮影(300〜500枚程度)
:バッテリー1本+予備1本 - 子どもの運動会・発表会(700〜1,000枚)
:2本以上推奨(連写が多いため) - 登山・長時間の屋外撮影
:2本+モバイル給電の組み合わせが安心
「撮らない時間も液晶が点きっぱなし」になりがちな人は、1.5倍〜2倍の消耗を見込んでおくのが現実的です。
動画:4K撮影・Vlogに必要なバッテリー量

動画撮影は、静止画と比べてバッテリーの消耗がはるかに激しいです。
特に4K60fpsや長時間撮影を行う場合、1本のバッテリーで持つ時間は1時間未満になることも珍しくありません。
撮影条件別の目安:
- 4K30p/1日30分程度の撮影:バッテリー2本+USB給電が安心
- Vlog撮影(1時間超)やライブ配信:最低でも3本、またはUSB給電前提
- タイムラプスやインタビュー撮影:ACアダプターまたはモバイルバッテリーの常用が前提
動画メインで活動する人には、USB給電対応モデル+大容量モバイルバッテリー(PD対応)の組み合わせが必須装備といえます。
節電の基本5テク(EVF設定・Wi-Fi・スリープほか)

以下の設定・運用を見直すだけでも、撮影枚数や録画時間が数割伸びることもあります。
1. EVF/液晶の明るさを抑える
明るさ設定が高いと、思った以上に消耗します。屋外でも自動調整に任せず、暗めをキープ。
2. スリープ時間を短めに設定
無操作時に自動で電源が落ちる設定(30秒〜1分)がおすすめ。これだけで1日単位の電池持ちがかなり変わります。
3. Wi-Fi・Bluetoothは使わないときはオフ
スマホ連携を常時オンにしていると、バックグラウンドで電力を消費します。必要な時だけオンに切り替えましょう。
4. 手ブレ補正を適宜オフ
三脚使用時はOFF推奨。常時オンにしていると、カメラ内部で無駄な補正動作が発生し、消費が増えます。
5. 撮影後のプレビューは短く
毎回撮った写真をじっくり見返すと、液晶点灯時間がかさみます。確認は必要最低限に。
「減らさない工夫」をすることで、今の状態でもバッテリー持ちを改善することはできます。気になっている方は、上記を見直してみるのも1つの選択です。
モバイルバッテリー&USB給電運用のポイント

これを活用すれば、バッテリーの持ちを気にせず、撮影中でもモバイルバッテリーから給電することができます。
運用時のチェックポイント:
- USB PD対応のモバイルバッテリーを選ぶ(18W以上推奨)
- 撮影中の給電が可能かは機種による(一部は給電のみで撮影不可)
- USBケーブルの質にも注意(出力不足だと電圧が足りず給電できないことも)
たとえば、Sony α7 IVやCanon EOS R6 IIは、PD対応のモバイルバッテリーから撮影しながら電源供給が可能で、実質「バッテリー無限運用」が可能になります。
次の章では、よくある悩みの1つ「純正と互換バッテリー、どっちを選ぶべき?」という疑問にお答えします。コスト・信頼性・安全性のバランスから見た選び方を解説していきます。
互換バッテリーってどうなの?安全に選ぶポイント
ミラーレスカメラの予備バッテリーを検討する際、必ずといっていいほど悩むのが「純正か?互換か?」という問題です。
純正バッテリーは安心だけど高価。互換バッテリーは安価だが品質が不安定――このバランスをどう考えるかは、多くのカメラユーザーにとって現実的な課題です。
このセクションでは、両者の違いやリスク、互換品を選ぶ際の判断基準を整理して、失敗しない選び方をお伝えします。
純正 vs 互換の違いとメリット・デメリット

まずは、純正バッテリーと互換バッテリーの主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 純正バッテリー | 互換バッテリー |
|---|---|---|
| 価格 | 高い(1個8,000〜15,000円程度) | 安い(2個セット+充電器で3,000円前後) |
| 品質の安定性 | 非常に高い(カメラ設計に最適化) | ピンキリ。個体差や初期不良もあり得る |
| 対応保証 | 正規保証対象(カメラの故障も保証対象) | 保証対象外(カメラ故障の補償は基本なし) |
| 長期信頼性 | 高寿命。数年使えることが多い | 数ヶ月〜1年でヘタる場合も |
一方、コスト面では互換が圧倒的に安く、「とりあえず枚数確保したい」という人にとっては魅力的な選択肢です。
ただし、粗悪な互換バッテリーによってカメラ本体が発熱・誤作動を起こすケースもあり、特に高額機種には不向きです。
安心して使える互換メーカーの条件

互換バッテリーを検討する場合は、信頼できるメーカーを選ぶことが重要です。以下のようなポイントに注目してください。
✔ PSEマークの有無
互換バッテリーも例外ではなく、PSEマークがないものは絶対に避けるべきです。
✔ 国内流通・サポートが明確なブランド
ROWA(ロワ)、Wasabi Power、Neewerなど、ある程度の歴史と評価があるブランドを選ぶことで初期不良やトラブル時の対応も受けやすくなります。
✔ Amazonやヨドバシ等の「レビューを確認」
レビューが100件以上あり、平均評価が4.0以上のものは一定の安心感があります。ただしサクラレビューには注意。
✔ パッケージの信頼性と製品登録
不自然なブランド名や、説明書が極端に簡素なもの、製品登録できないものは避けたほうが無難です。
安さ重視?安心重視?買い方の指針

結局のところ、「純正と互換のどちらを買うか」はそのカメラにどれだけ投資するか・失敗をどれだけ許容できるかによって判断が分かれます。
▶ 安全性最優先なら純正一択
新品で買ったばかりのフルサイズカメラや、業務利用を前提とする機材では、互換品を使って故障や保証外トラブルを起こすリスクは回避すべきです。
▶ コスト重視・割り切り派なら互換も選択肢
ミラーレス入門機や、中古で購入したサブ機など、ある程度の割り切りができる場面では、実績ある互換バッテリーを選ぶことでコストパフォーマンスは格段に上がります。
▶ ハイブリッド運用もアリ
「メインは純正」「予備として互換」など、場面や優先度に応じて使い分けるのも現実的な選択です。互換の初期不良も含めて、数本持っておくと安心です。
まとめ:ミラーレスの電池持ちは「選び方&使い方」で解決できる
「ミラーレスは電池が持たない」という印象は確かに一理あります。
しかし、それは構造的な特性であって、最新機種や運用の工夫次第で十分にカバーできる問題です。
現在のミラーレスは、以下のような対策・選び方を押さえることで、電池切れの不安を大きく軽減できます。
✅ バッテリー持ち対策の要点まとめ
- 電池持ちが良い機種を選ぶ(CIPA基準で500枚以上が目安)
- USB給電・バッテリーグリップ対応機種を活用する
- スリープ設定・液晶の明るさ・Wi-Fi/Bluetooth設定を見直す
- 静止画中心なら予備バッテリーは1〜2本でOK
- 動画メイン・長時間撮影ならUSB給電+3本体制が安心
- 互換バッテリーを使う場合はPSEマークと信頼性を重視
初めてミラーレスを使う人なら、まずはこのチェックリストを参考に、「予備1本+節電設定」から始めるだけでも十分効果を感じられるはずです。
カメラの性能を最大限活かすためにも、機種選びと使い方の両面から備えて、安心して撮影を楽しみましょう。