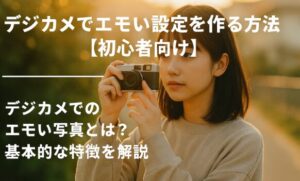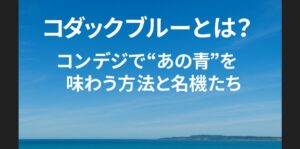「オリンパスのカメラはやめとけって聞いたけど、実際どうなの?」
「買って後悔する前に、リアルな口コミや評判を知りたい」
そんな風に検索しているあなたは、今ちょうどOM SYSTEM(旧オリンパス)のカメラ購入を迷っているのではないでしょうか?
ネット上では「買わない方がいい」「UIがわかりにくい」「ブランド売却が不安」など、ネガティブな声もちらほら見かけます。
一方で、「軽くて旅に最高」「発色が美しい」「手ぶれ補正が神レベル」といった熱烈なファンも多く、“真逆の評価”が共存しているのがこのメーカーの特徴です。
そこで本記事では、
- 実際に「やめとけ」と言われる理由は何なのか?
- どんな人にはおすすめできないのか?
- 逆にどんな人にとって“ベストな選択”になるのか?
- 最新モデル「OM-3」や人気モデルの口コミ・評判・価格帯は?
といったポイントを、実在するレビューや専門家の意見をもとにわかりやすく・冷静に解説していきます。
最後まで読めば、「買う or 見送る」の判断がきっとクリアになるはずです。
それではさっそく、「やめとけ」と言われる理由からチェックしていきましょう。
オリンパスのカメラを「買わない方がいい」と言われる4つの理由とは?
「オリンパスのカメラ、やめといた方がいいんじゃない?」
これはSNSや掲示板、レビューサイトなどでたびたび見かける声です。かつては“玄人好みの名機”と称されていたオリンパス(現OM SYSTEM)のカメラが、なぜこんな風に語られるようになったのでしょうか?
ここでは、よく挙げられる「買わない方がいい」と言われる理由を、4つに絞って紹介します。
① 高すぎる?価格とスペックのバランスに不満の声

まず最もよく言われるのが「価格に対する満足度が低い」という点です。
最新モデル「OM-3」は、実勢価格で20〜25万円前後。スペックや性能は申し分ありませんが、同じ価格帯にはフルサイズセンサー搭載のソニーα7C IIやニコンZfなどの競合がひしめいています。
noteユーザー@photolife1961さんのレビューからは、こうした不満が明確に読み取れます。
「使わない機能がてんこ盛りで単に値段が高いだけのカメラとなってしまい「今は買わないカメラ」となりました。」
もちろんOM-3には優れた防塵防滴性能や手ぶれ補正がありますが、“価格の壁”を超えるだけの魅力を感じられない層も確かに存在するのです。
② 操作性やUIにクセがある?

設定項目の多さ、メニューの階層の深さ、そしてカスタマイズの自由度——それらは一見メリットですが、初心者には“使いこなせない不安”を生む要因にもなっています。
価格.comのユーザーレビューでも、
「OMワークスペースについて
とにかく分かりにくくて、とてもモッサリした動作をします。」
価格ドットコムより
といった声があり、UIが万人向けではないことが分かります。
③ OM SYSTEMという新ブランドに対する不安
かつての「OLYMPUS」ロゴは、多くのユーザーにとって信頼の証でした。
しかし2020年、カメラ事業はオリンパス本体から分離され、新会社OMデジタルソリューションズへ。ブランド名も「OM SYSTEM」に変更されました。
これに対し、Yahoo知恵袋ではこんな投稿も:
「少なくとも暫くはOLYMPUSブランドとして残る予定です。10年後20年後は分かりませんが」
– 出典:Yahoo!知恵袋
ブランドへの信頼性がカメラ選びの決め手となる層にとっては、ブランド移行はネガティブ要素になっているのは確かです。
④ スマホで十分?という時代背景
カメラ性能がバカ高いスマホがあれば一眼レフ正直いらないしこれからもスマホカメラの性能向上に期待
— Cの日常 (@kurohanoru) May 10, 2024
もう一つ大きいのは、「そもそも今カメラ買う意味あるの?」という根本的な問いです。
「手軽に綺麗に撮れる」ことに価値を感じる多くの人にとって、わざわざカメラを持つメリットが薄れているのです。
実際、SNSではこんな意見もよく見かけます。
「もうスマホで全部撮ってる。カメラ買う意味が分からない」
「インスタに上げるならスマホで十分」
こうした「カメラ不要論」は、オリンパスに限らずコンパクト・ミラーレス全体が直面している共通の壁でもあります。
このように、「オリンパスを買うな」「やめとけ」といった声には、それなりの理由が存在します。
ですが、それが「すべての人に当てはまる」とは限らないのもまた事実。
次章では、実際に「買ってよかった」というユーザーの声も紹介していきます。
実際の口コミはどうなのか?リアルなユーザーの声まとめ

前章で紹介した通り、オリンパス(OM SYSTEM)のカメラには「買わない方がいい」と言われる理由がいくつかあります。
このセクションでは、実際のユーザーによる「ネガティブな声」と「ポジティブな声」を両方紹介し、オリンパスカメラの評価がなぜこんなに割れるのかを見ていきましょう。
▼ ネガティブな口コミ(掲示板・note・知恵袋など)
まずは、やや厳しめのレビューから見ていきます。
これは「買わない方がいい」という印象を強く持つ読者が気になる部分でしょう。
「値段の割に細部の作りがちょっとなーという感じで、」
– 価格.com レビュー(OM-3)
「乱暴な言葉で申し訳ない。OM SYSTEMはヤメレ!!ダサすぎる。」
– note投稿
「課題はメニュー構造とEVFの見え方だけ」
– 価格.comレビュー(OM-D E-M1 Mark II)
これらの声に共通しているのは、
- 価格に対する所有感や質感へのギャップ
- 操作性やUIの直感性の欠如
- ブランド移行によるアイデンティティの喪失感
など、感情的な落差に起因するものが多い点です。
▼ ポジティブな口コミ
それらは「写真を楽しむ」「機材との一体感を感じる」人たちの声です。
「このカメラには完全に可動式のスクリーンが搭載されており、これは非常に便利な機能なので、いくら強調しても足りないほどです。」
– Sam Davis 氏(フォトグラファー、OM-5レビュー)日本語訳
「見た目も手触りも高品質なデバイスで、手に取って使うのが楽しくなります。」– Fstoppers “The New OM-1…”レビュー
これらの口コミから見えてくるのは、
- 軽量・高性能な撮影体験
- 操作の気持ちよさ・所有感
- 色表現・描写力への高い評価
といった“体験に価値を感じるタイプの満足感”です。
評価が分かれるのは「カメラに何を求めるか」の違い
オリンパスの評価が極端に分かれる理由は、スペックやブランド力の問題だけではありません。ユーザー自身が「カメラに何を求めるか」によって、評価が正反対になるからです。
- 機能より“楽しさ”や“道具感”を求める人にとっては、OM SYSTEMは非常に魅力的。
- 逆に、「とにかく性能最強であること」や「ブランド力・プロ用途」を重視する人には、やや物足りなさを感じるのも確か。
だからこそ、購入を検討する前に「自分がカメラに求めるものは何か?」をはっきりさせておく必要があります。
次章では、そうした視点を踏まえて「それでもオリンパスを選ぶ人」がどんな人なのか、なぜ満足しているのかを解説していきます。
それでもオリンパスを選ぶ理由:満足する人の3つの共通点
前章までで「オリンパスはやめとけ」と言われる理由と、それに共感するユーザーの声を見てきました。
では、彼らはどんな人たちなのでしょうか?
口コミやレビュー、YouTubeの実機体験レポートをもとにすると、オリンパスユーザーに共通する3つの価値観が見えてきます。
① 小型・軽量&強力な手ぶれ補正で「旅カメラ最強」

OM SYSTEMの主力であるOM-1やOM-5は、マイクロフォーサーズセンサーを採用しているため、ボディ・レンズともに非常に小型軽量。
OM-1は599gと、同等クラスのフルサイズ機より200〜300g軽く、望遠レンズをつけてもバッグにすっぽり収まるサイズ感が魅力です。
特に登山や旅行、街歩き撮影をする人にとっては、「カメラを持ち出すハードルが低い」というのが大きなメリットになります。
加えて、OM SYSTEMのもう一つの武器が圧倒的な手ぶれ補正。OM-1では最大7段、組み合わせによっては8段近い補正も可能です。
「山へ行く際は少しでも装備が軽い方が望ましいが、OM-5は約366gと軽いので苦にならず、カメラバッグにほんの少しのスペースがあれば入れることができる。」
– デジカメwatch(OM-5)

② 操作の楽しさ・“写欲”を引き出すシャッター感

「軽い・高性能」だけではありません。
オリンパス(OM SYSTEM)が根強いファンを持ち続けている理由のひとつが、操作そのものの“気持ちよさ”です。
シャッターを押す感触、ダイヤルを回す音、グリップのフィット感……それらが“写真を撮る”という体験を楽しくするのです。
クラシカルで小柄なボディは使っていて気分良く、操作していて楽しくなりました– デジカメWatch(OM-3)
これは数値には表れにくいポイントですが、実はカメラにとってとても重要な要素。
多くの人が「フルサイズを持っていても、オリンパスを手放さない」のは、まさにこの“写欲”の心地よさに魅了されているからです。
③ 独自の色味や描写に魅力を感じるユーザー多数
おはようございます。
— ブースカ (@buska_photo) October 15, 2024
季節外れの?
いやいや、つい最近のひとコマ🌻
佐倉ふるさと広場の近く。
今年も秋のヒマワリを楽しませてもらいました。
青い空、今もオリンパスブルーは健在です。
202410.12撮影#OMSYSTEM #TLを花でいっぱいにしよう pic.twitter.com/lxrkU3MOsZ
OM SYSTEMのカメラは、JPEG撮って出しでも色表現が非常にナチュラルで、特に空や海、自然の緑を撮影したときに他社とは違う“透明感”が出ると評価されています。
このように、レタッチに時間をかけずに“気持ちよく撮って出し”をしたいユーザーにとって、オリンパスは非常に相性の良いカメラだといえるでしょう。
満足している人は“数字に出ない価値”を求めている
ここまで見てきたように、OM SYSTEMのカメラを愛用している人は、
- スペック表よりも携帯性・感触・写欲を重視
- 色表現や操作性など“写真体験の楽しさ”を大切にしている
といった傾向があります。
だからこそ、スペック比較で勝負するフルサイズ機とは、そもそも求めている世界が違うのです。
次章では、これまで紹介した強みをふまえ、他社カメラと比較したときにどんな違いがあるのかを具体的に見ていきます。
【比較】OM SYSTEM vs 他社:どんな違いがある?
オリンパス(OM SYSTEM)のカメラに魅力を感じる一方で、多くの人が最後に悩むのが、
「同じ価格帯ならフルサイズが買えるのでは?」
という点です。これは実際に正しい指摘で、OM SYSTEMの上位機「OM-1」や「OM-3」は、20万円台後半というフルサイズ機に匹敵する価格帯にあります。
ここでは、OM-1を代表例に、同価格帯のライバル機種と比較してみましょう。
OM-1とライバル機の比較表
(2025年7月時点)
| 項目 | OM SYSTEM OM-1 | ソニー α7C II | ニコン Zf |
|---|---|---|---|
| センサーサイズ | マイクロフォーサーズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2037万画素 | 約3300万画素 | 約2450万画素 |
| 重量(バッテリー込) | 約599g | 約514g | 約710g |
| ボディ内手ぶれ補正 | 最大7段分 | 約5段分 | 約5段分(実測) |
| 防塵・防滴 | ◎ 高い | △(簡易防滴) | ◎ 高い |
| 実勢価格帯 | 約22万〜24万円 | 約27万〜30万円 | 約28万〜31万円 |
※ 各種メーカー公式、価格.com、マップカメラ調査値(2025年7月時点)
比較して見えてくるOM SYSTEMの「強み」と「弱み」

この表を見ると、OM SYSTEMのカメラは、センサーサイズ(=画質)では他社に劣ることがわかります。
特にボケ量や高感度ノイズ性能では、フルサイズが優位です。しかし、それを補って余りある以下のポイントが存在します。
✅ 強み①:小型軽量・高耐候性能
599gという軽さは、防塵防滴仕様の中級機としては非常に優秀。Zfは710g、α7C IIもレンズ込みでは700g超えが普通です。
加えて、OM-1は-10℃耐低温設計、防滴構造(IP53相当)と、アウトドアでの信頼性はトップクラス。登山や悪天候でも安心して使えるタフな機材です。
✅ 強み②:手ぶれ補正が別次元
最大7段(組み合わせ次第で8段近く)という手ぶれ補正は、夜間や望遠撮影でも手持ちが可能なレベル。
特にOM SYSTEMの「ライブND」「手持ちハイレゾショット」など、実用的かつ“ワクワクする機能”が多いのも特徴です。
⛔ 弱み:画質(特に高感度・ボケ)ではフルサイズに軍配
これは正直に認めるべきポイントです。
物理的にセンサーが小さいマイクロフォーサーズは、高感度耐性や背景ボケ量でフルサイズに劣ります。
ただし、その差は「作品づくりにこだわるプロ」レベルでなければ、大きな問題にならないという声もあります。
結論:数字だけで比べると不利、でも“実際の使い勝手”は人による

この比較からも分かるように、OM SYSTEMは「スペック表だけで判断すれば不利」に見えます。
しかし、防滴・軽さ・補正機能など“現場で活きる性能”に特化している点が最大の魅力です。
写真を作品として極めたい人、被写界深度の浅さ(ボケ感)を重視する人はフルサイズが合います。
でも、「軽くて楽しく撮れて、持ち出しやすく、信頼性も高いカメラ」が欲しいなら、OM SYSTEMは唯一無二の選択肢になり得ます。
オリンパスが向かない人の特徴(=やめとけ対象)

どんなに良いカメラでも、全員にフィットする“正解”は存在しません。
OM SYSTEMの魅力を語ったあとだからこそ、冷静に「オリンパスが向かない人」の特徴を確認しておきましょう。
1. フルサイズのボケ感や画質にこだわる人
マイクロフォーサーズは構造的に被写界深度が深くなるため、フルサイズのような「とろけるようなボケ」は得られにくいのが現実。
「開放F1.2のレンズを使えばいい」という意見もありますが、それなら最初からフルサイズのほうが選択肢も豊富です。
2. スペック至上主義・スペックで選びたい人
「この価格でセンサーが小さいのはナンセンス」と思ってしまうタイプの方は、数字の上でOM SYSTEMに満足するのは難しいかもしれません。
スペック表ではα7シリーズやZシリーズに軍配が上がる場面が多く、オリンパスは“使ってこそわかる”良さが光るブランドです。
3. サードパーティ製レンズを多用したい人
SIGMA・TAMRONといったサードパーティ大手も、フルサイズ用に力を入れているため、レンズ資産を重視する人にはやや不利かもしれません。
逆にオリンパスがぴったりな人の特徴
次のような価値観を持っている人には、むしろぴったりハマるでしょう。
1. 軽くて持ち運びやすい“旅カメラ”を探している人
「大きくて重いカメラは使わなくなる」
これは、カメラ初心者〜中級者の方が口を揃えて言う“あるある”です。
OM SYSTEMのカメラとレンズはとにかく軽量。しかも防塵防滴・手ぶれ補正付きで信頼性も高いので、登山・旅行・街歩きなど、“歩きながら撮る”人にとっては最適解です。
2. 写真を“道具としての楽しさ”で選びたい人

操作感、ボタンの配置、ダイヤルのクリック感…。
それは数値では測れない「所有する喜び」や「撮るモチベーション」に直結します。
3. JPEG撮って出しで“そのまま使いたい”人
後から編集しない、または最低限しか加工しないという人にも、OM SYSTEMは非常に向いています。
「オリンパスブルー」と呼ばれる独特の発色や、優れたAWB(ホワイトバランス)性能によって、JPEGでも“撮ったままの美しさ”が成立するのが特徴です。
編集に時間をかけたくない、でも色にはこだわりたいという方には、この写りの方向性がぴったり合うでしょう。
つまり、選ぶべきは「スペック」ではなく「価値観」
- 作品としての一枚を極めたい ⇒フルサイズ
- 日常を切り取る・旅先で感性のままに撮りたい ⇒OM SYSTEM
その違いを理解したうえで、「自分に合うか?」を考えると、判断がぐっとラクになります。
【おすすめモデル紹介】用途別の最適な1台はこれ!
ここまで読み進めてきて、「オリンパスカメラ、自分には向いているかもしれない」と感じた方も多いかもしれません。
でも、そこでまた出てくるのがこの疑問。
「OM SYSTEMの中で、どのモデルを選べばいいの?」
現在、OM SYSTEM(旧オリンパス)はラインナップがやや分かりづらくなっています。
ここでは、あなたの用途・撮影スタイルに合ったおすすめモデルを3タイプに分けてご紹介します。
初心者〜中級者におすすめ:OM‑5 / E‑M10 Mark IV

▶ こんな人に向いている:
- スマホしか使ってこなかったが、初めてカメラを買いたい
- できるだけ軽く、手軽に始めたい
- でも妥協せず、しっかりとした機能がほしい
OM‑5は、OM SYSTEMブランドでの中堅機。E-M10 Mark IVはさらに軽量で、非常に扱いやすく、価格も抑えめ。
どちらも有効画素数は約2000万画素前後で、手ぶれ補正やバリアングル液晶を搭載。
日常のスナップや旅写真にはぴったりです。
✅ 「軽くて気軽に持ち出せる」「JPEGがきれいでそのまま使える」など、満足度が非常に高いモデルです。
本格派・アウトドア派におすすめ:OM‑1 Mark II

▶ こんな人に向いている:
- 登山・アウトドア・スポーツ撮影など、過酷な環境でも使いたい
- 雨や雪でも気にせず撮りたい
- RAW現像や本格的な撮影にも対応したい
OM‑1 Mark IIは、現行OM SYSTEMのフラッグシップ機。高耐久ボディ、防塵防滴(IP53)、最大8段分の手ぶれ補正、120fpsの高速連写など、性能・機能は全方位にすぐれています。
✅ 「三脚いらずで夜景が撮れる」「雪山でも壊れない」といった信頼性の高さは、他社製品では代替しづらい魅力です。
価格は高めですが、「一生使える1台が欲しい」という方には最適な選択肢になります。
中古でコスパを狙う人に:PEN-F / E-M1 Mark II

▶ こんな人に向いている:
- 新品にはこだわらない
- デザイン性や写りに“味”を求めたい
- できればコスパ良く、良質なカメラを手に入れたい
PEN-Fは、2016年発売ながら未だに熱狂的ファンが多い“名機”。レンジファインダー風のデザインと、独自の色彩コントロールで「写欲が刺激される」と評価されています。
E-M1 Mark IIは、OM SYSTEM前身のOLYMPUS時代のハイエンド機。現在は中古価格がかなり落ち着いており、5〜7万円台で高性能が手に入ります。
✅ 中古でも充分な性能が得られ、第一線で活躍できるモデルです。初期投資を抑えたい方にぴったり。
✳️ 購入時の注意点
- 防塵・防滴機能はモデルによって差があるため、使う環境を意識して選ぶことが大切
- 中古モデルを買う場合は、シャッター回数・バッテリー劣化・ファームウェア対応状況も確認を
【よくある質問(FAQ)】
Q. オリンパスのカメラは本当に「やめとけ」なんですか?
A. 一部の人には確かに向いていませんが、すべての人に当てはまるわけではありません。
「やめとけ」という声の多くは、
- フルサイズと比較した際のセンサーサイズ
- ブランド移行に対する不安
- 高価格帯に対する期待ギャップ
などから生まれています。
ですが、求めるものが“軽さ・携帯性・扱いやすさ・発色”であれば、むしろ最適な選択肢になる可能性が高いです。
Q. マイクロフォーサーズってもう時代遅れなんですか?
A. 一部の高感度領域では限界がありますが、OM SYSTEMは進化を続けています。
むしろ、「小型軽量・高精度の手ぶれ補正・手持ち高解像撮影」など、他社が追いつけない分野で先行している側面もあります。
日常使いや旅、山など「行動しながら撮る」スタイルには非常に適しています。
Q. OM SYSTEM(旧オリンパス)は今後も続きますか?
A. OMデジタルソリューションズとしてブランドは継続中で、新製品も定期的に発表されています。
確かにOLYMPUSからは独立しましたが、技術陣はそのまま継続して開発を行っており、信頼性は高いと評価されています。
【結論】オリンパスは買わない方がいい?本当に向いているのはこんな人!
本記事では、「オリンパスカメラはやめとけ」と言われる理由と、その実態を多角的に検証してきました。
確かに、万人にとっての“最適解”ではないかもしれません。ですが、それでもオリンパス(OM SYSTEM)を選び続ける人には、明確な価値観があります。
✅ オリンパスが本当に向いているのはこんな人!
- 大きくて重いカメラにはうんざりしている
- 撮影そのものを“気軽に・楽しく”したい
- JPEGでもきれいに写る、信頼できるカメラが欲しい
- 毎日持ち歩ける“相棒”としてのカメラを探している
- 過酷な環境でも壊れにくいカメラが欲しい(登山・旅行・雪山など)
スペック比較では見劣りしても、「使って楽しい」「撮って満足できる」カメラは、人生の思い出を豊かに残してくれます。
オリンパス(OM SYSTEM)は、まさにそんな“使う人の心に寄り添うカメラ”だといえるのではないでしょうか。
✅ 迷っている方へ:まずは価格やレビューをチェック
📸 【Amazonで OM-1 の価格を見る】
Amazon
📸 【楽天で PEN-F の在庫を探す】
Rakuten
📸 【OM SYSTEM公式ストアはこちら】
OM SYSTEM STORE
📸 【カメラのキタムラで探してみる】
カメラのキタムラ ネットショップ
最後に:
「買わないほうがいい」と決めつける前に、
“どんなカメラライフを送りたいか”を考えてみてください。スペックでは測れない満足感が、あなたを待っているかもしれません。