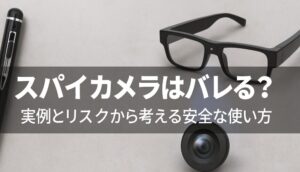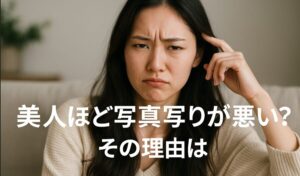「いつも写真を撮る側」になってしまう…。
そんな悩みを抱えながら検索にたどり着いたあなたは、おそらく何度も同じ場面を経験してきたはずです。
- 「写真撮ろうよ」と言い出すのに、なぜか自分ではカメラを出さない友達。
- 「撮って」と頼んでくるけれど、自分が撮られることには消極的な撮らせる人たち。
一緒に楽しんでいるのに、自分の姿が写真に残らないという寂しさや、毎回撮影係になることへのモヤモヤを感じている方は少なくありません。
この記事では、「なぜいつも撮る側になってしまうのか?」という心理や背景から、撮られたい気持ちを叶える工夫や、バランスの取れた関係を築くためのヒントをお届けします。
もう「記録係」だけで終わらせない、あなたのための写真のあり方を、一緒に見つけていきましょう。
本記事を読んで分かること
- いつも写真を撮る側になる人の心理や特徴
- カメラを出さない友達や撮らせる人達の背景
- 撮る側ばかりで写らない状況から抜け出す方法
- 撮る側で感じるモヤモヤや不満への向き合い方
いつも写真を撮る側になってしまう人の心理と理由
写真を撮るとき、なぜか毎回「撮る側」になる人がいます。
自分のカメラを渡して撮ってもらいました!いつも撮る側で撮られる事がほとんどないので自分の写真が残るのメチャクチャ嬉しい。
— ショウRR (@CBR_Syo39RR) April 14, 2025
photo by @u__cbrgsx97 ←💪プロ級#CBR250RR pic.twitter.com/coneHcpLz0
いつも写真撮る側の人間だったから撮られなれてない🫠
— 雨流5/10.11池a! (@Sameru_21) April 25, 2025
「撮ってあげるね」と自然にカメラを構える側の人もいれば、「お願い!」と撮られる側に回る人も。
この構図には、性格的な傾向や人間関係の距離感が関係しています。
ここでは、そんな「いつも撮る側」になる人の心理や、撮られることを避ける人たちの理由をひも解いていきます。
カメラを出さない友達の心理とは

「写真撮ろうよ」と言い出すのに、自分では一切カメラを出さない…。
そんな友達にモヤっとした経験、ありませんか?
この行動の背景には、「面倒くさい」「楽をしたい」「送ってもらえるとわかっている」といった思考があります。
自分で撮らないことで、手間も省けてスマホの容量も節約できる。

そして、「あなたがいつも撮ってくれるから大丈夫」と、無意識に甘えているのです。
また、「撮るのが苦手」「下手に撮って嫌な気持ちにさせたくない」など、自信のなさが隠れている場合もあります。
どちらにせよ、「自分では撮らないけど撮ってほしい」という姿勢は、相手任せのスタンスと言えるでしょう。
写真を撮る人が抱えるモヤモヤの正体
写真撮影は嫌いじゃない、むしろ好きな方かもしれない。

でも、いつも撮る側に固定されると、だんだんと「わたしは記録係?」という虚しさが湧いてきます。
「楽しんでいる風景は残るのに、私はどこにも写っていない」
アルバムを見返すたび、そこに自分の姿がないと、思い出の共有から外れているような寂しさも。
さらに、「なんで私ばっかり?」「自分勝手じゃない?」という不公平感やイライラも重なってくることがあります。
対策としては、「今日は私も写りたい日なの」と明るく伝えてみること。
言わないと伝わらないこともあるので、遠慮せずに一言添えるのがおすすめです。
写真を撮る側の人にありがちな特徴とは

「撮る側」になりやすい人には、いくつかの共通点があります。
たとえば、
- 人間関係において「空気を読む」ことが多い
- 自分が写ることにあまり執着がない
- 人の笑顔を引き出すのが好き
- 気配りができる
といった傾向が見られます。
また、カメラに慣れている・撮影スキルが高いなど、「頼りにされる要素」があると、自然とカメラ役を任されがち。
さらに、「自分が写るのはちょっと苦手…」という自己イメージの控えめさがあると、あえて撮る側にまわることもあります。

その場にいたことを未来の自分や家族に伝えるためにも、「自分も写ること」の大切さを意識してみてください。

いつも写真を撮る側ばかりで写らない悩みの解決策
そんな悩みを持つ人は、実はとても多いです。
ここでは、撮る専門から脱出し、自然に“写る人”になるためのヒントや工夫を紹介していきます。
楽しく記録を残すために、ちょっとした発想の転換やアイテムが役に立つこともありますよ!
📸自然に「一緒に撮る」流れを作るには
「撮ってばかりじゃなくて、一緒にも撮りたい!」でも、自分から言い出すのはちょっと気が引ける…。

グループで出かけた時はタイミングを見て、
ここ景色きれい!せっかくだから一緒に撮ろ〜
このお店の前、全員で撮ったら思い出になるよ!
と、自然なシチュエーションを演出してみてください。
また、「撮ってもらってもいい?」ではなく、「一緒に写ろう!」という表現にするだけでも印象が違います。
“撮ってもらう=お願い”より、“共有する=対等な関係”になります✨
🎯自分も写るためのアイデア・工夫
撮る側が写るには、ちょっとした準備や小道具が力になります!

🌟 三脚+スマホのリモコンシャッター
→ 軽量で持ち運びやすく、旅行や公園でも大活躍。タイマー撮影よりも自然な笑顔が撮れます。
🌟 「撮ってくれる人を固定しない」ルール
→ 旅行前に「今日は交代でカメラ係ね!」と提案しておくと◎。役割の偏りを防げます。
🌟 インカメラ・広角レンズで“自撮り風集合”
→ 「セルフィー棒は恥ずかしい」人には、手で持って広角で撮るだけでもOK!
🌟 ストーリーや動画と一緒に静止画も残す
→ 動画なら自然体が撮れるし、あとからスクショでお気に入りを切り出せます🎥📷
アイテムを味方につけて、撮る楽しさ+写る嬉しさを両立させましょう!

🗣撮る側を卒業するコミュニケーション術

撮るのが好きでも、「毎回はちょっと疲れる…」と感じたら、きちんと伝えることも大事。
でも、怒りや不満ではなく、ユーモアや気遣いを交えて伝えるのがコツです✨
たとえば、こんな言い方はいかがでしょう?
🔹「今日はカメラ係おやすみしたい日だから、バトンタッチお願いしてもいい?」
🔹「そろそろ私も写りたいな〜、いい感じに撮ってくれる人募集!」
🔹「今度は○○ちゃんのカメラで撮ってみて!どんな風に写るか楽しみ〜」
相手を責めずに“お願い+好意”の形にすると、印象が柔らかくなります。
もしそれでも変わらないなら、
「自分でやらないと伝わらないタイプかも」と受け入れた上で距離感を見直す
というのもひとつの方法です。
「写真を撮る側」の不満を解消するために
写真を撮るのは好き。
けれど、「当然のように頼まれる」「感謝されない」「自分の姿が思い出に残らない」…そんな積み重ねが、じわじわと心にモヤモヤを残します。
このセクションでは、その不満を自分の中でどう整理し、どんなふうに軽くしていけるのかにフォーカスしてみましょう。
🎭 写真係を「演じる」自分に気づいてみる
あなたが撮る側にまわるのは、技術的な理由だけではないかもしれません。

「みんなの楽しさを残してあげたい」「自分は裏方でいい」という“気配り役”としての役割を、自分で背負っている可能性もあります。
📌まずは、「どうして自分は撮る側でい続けてきたのか?」と、自分のパターンに目を向けてみましょう。
それは気遣いかもしれないし、目立ちたくない気持ちかもしれません。
いずれにしても、「自分で選んでいる部分がある」と気づくだけで、少し気持ちが整理されます。
「モヤモヤ」は他人ではなく、自分にヒントがある
人に頼まれたり、感謝されなかったりすることが続くと、「なんで私ばっかり?」という怒りが湧いてきますよね。

- 期待していた「ありがとう」がなかった
- 「撮ってほしい」と言えず我慢してしまった
- 「一緒に撮って」は自分から言いづらい
📍そんな小さな“期待と現実のズレ”が、蓄積すると不満になります。
だからこそ、「どうされたいか」より、「どう感じているか」に目を向けてみてください。
すると、「私は無視されてるんじゃない、伝えてなかっただけかも」と視点が変わります。
✨ “ありがとうがない”の対処は、受け取り方の再設計から
「感謝されない」のは、つらい。
でも、それを責めるでもなく、自分の中で“どう受け取るか”の設定を見直すこともできます。

たとえば、
🔹「ありがとう」と言われないけど、笑顔や楽しそうな顔で喜んでくれていたかも?
🔹期待しすぎず、自分が「撮りたいから撮った」と割り切ってみる
🔹一度だけ「ありがとうって言ってもらえると嬉しい」と軽く伝えてみる

💡「写らなかった自分」も愛おしむ視点

そう落ち込む日もあると思います。
でも、ちょっとだけ視点を変えてみてください。
「カメラの向こうから笑っていた自分」も、そこにちゃんと“いた”証なのです。
- 自分の手で切り取った誰かの笑顔
- シャッター越しに感じた幸せな空気
それも、立派な「わたしの思い出」だと認めてあげましょう。
もちろん、写りたい気持ちがあるなら、それも大切にして良いのです。
でも、写っていない=存在していないわけじゃないという視点が、自分を少し救ってくれるかもしれません。
このように、「写真を撮る側」の不満は行動のテクニックではなく、“感情の整理”や“自分との対話”によって解消に向かうことも多いのです。
いつも写真を撮る側の人が抱える悩みと向き合い方のまとめ
「いつも写真を撮る側」になってしまう人は、性格や人間関係の影響を受けてその役割に収まっていることが多いのかもしれません。
でも、自分の気持ちや存在も同じくらい大切にしていいのです。
撮る楽しさと、写る喜びのどちらも味わえるように、少しずつバランスを見直していきましょう!
本記事のポイントまとめ
- 撮る側になる人は気配りができ、空気を読んで動くタイプが多い
- 写ることへの抵抗感や自己評価の低さから自ら撮る側にまわる場合もある
- 写真を撮るのが好きな人ほど、無意識にカメラ係を引き受けてしまう傾向がある
- 自分が写らないことに対して、あとから虚しさや孤独を感じやすい
- 「撮って」と頼まれるのが当たり前になると、不公平感が積もる
- 撮られない悩みは、「一緒に写ろう」と自然に巻き込む言葉で対処できる
- 自分の写りを増やすには三脚やリモコンなどのアイテム活用が効果的
- 写真係を固定化させないためには事前の役割シェアが有効
- ユーモアや軽さを持って「今日は撮られたい」と伝えることが大事
- 不満が募る前に、ありがとうが欲しい気持ちを正直に伝えることが解決につながる
- 「感謝されない」は相手の悪意ではなく、文化の違いと捉えると気が楽になる
- 「自分がなぜ撮る側になり続けているのか」を内省することも有効
- 期待と現実のズレが不満の正体であることが多い
- 写っていなくても、シャッターを押した記憶もまた大切な思い出になる
- 撮る側をやめたい時は、無理せず一度距離を置いてもいいという選択肢を持つ